就業規則の作成・変更
法改正への対応はできていますか?
社会保険労務士 江尻育弘
 就業規則はよく「職場のルールブック」と言われますが、近年、その重要性は高まる一方です。労働トラブルや社員との行き違いなどの原因を分析してみると、その多くは就業規則等において社内ルールを明確にしておけば未然に防ぐことができ、また人材不足時代の人材の定着を考えると、社員に安心・納得して勤務してもらえるような環境の整備も重要になってきます。育児介護休業法など、細かい法改正も頻繁に実施されており、そうした改正にも随時対応していかなければなりませんし、更にはSNSの普及やメンタルヘルス不調者、ハラスメント問題の増加といった環境変化への対応も欠かせません。過去10年間に法改正以外の抜本的な規程改定を行っていない企業は注意が必要です。
就業規則はよく「職場のルールブック」と言われますが、近年、その重要性は高まる一方です。労働トラブルや社員との行き違いなどの原因を分析してみると、その多くは就業規則等において社内ルールを明確にしておけば未然に防ぐことができ、また人材不足時代の人材の定着を考えると、社員に安心・納得して勤務してもらえるような環境の整備も重要になってきます。育児介護休業法など、細かい法改正も頻繁に実施されており、そうした改正にも随時対応していかなければなりませんし、更にはSNSの普及やメンタルヘルス不調者、ハラスメント問題の増加といった環境変化への対応も欠かせません。過去10年間に法改正以外の抜本的な規程改定を行っていない企業は注意が必要です。
江尻事務所が作る就業規則の強み
ある時、労働基準監督署から是正勧告のあった企業から就業規則変更の依頼がありました。なぜ是正があったのかと聞くと、就業規則は法律通りなのだが、実態とかけ離れているとのこと。これまで多くの事業所の就業規則見てきましたが、現行の就業規則と現場の実態とが乖離していることが多々ありました。このギャップは賃金と労働時間に多く現れます。
私達社会保険労務士 江尻事務所は、このギャップを埋める就業規則の作成を得意としています。就業規則は社労士が一人で作って納品するわけではありません。お客様と一緒に顔を合わせて、何度も話し合いながら実態を把握し、社内にある具体的な問題を解決をする。私たちはそんな就業規則づくりをしています。
【事例1】就業規則・本則
◆労働時間の整備(年次有給休暇を与えることができないほど忙しい会社のケース)
| 行ったこと | 得られた効果 |
|---|---|
| 年間休日の再設定、年間労働時間の組み直し | 年次有給休暇を取れるようになった。 |
【事例2】賃金規程
◆課長と係長の給与の逆転現象の解消
◆新人と先輩社員の給与の逆転現象の解消
| 行ったこと | 得られた効果 |
|---|---|
| 管理者手当の水準見直し | 課長のモチベーションが戻り、働き方が良くなった。 |
| 基本給の歪み解消 | 先輩社員の不満が収まった。 |
就業規則の作成や改定にあたっては下記の点に留意して作成いたします。
- 法改正への対応
※直近では同一労働同一賃金があります。同一労働同一賃金に対応した規程の作成のためには現状の把握が欠かせません。弊所社労士の江尻は沖縄では唯一の厚生労働省認定の「職務分析・職務評価コンサルタント」です。2019年では4件、2020年では4件のコンサルティングを行っています。
職務分析・職務評価コンサルティングについてはこちらから › - 法律と現状のすり合わせ
- 重要な職場環境の変化への対応
- 多様化する労働時間関係の規定整備
- メンタルヘルス不調に対応した休職規定整備
- 増加する非正規社員の規程整備と無期転換ルールへの対応
- 育児介護休業法など最近の法改正への対応事項の確認
- 今後求められる多様な働き方への対応
- 会社の想いを社員に効果的に伝える就業規則の表現方法の工夫
- 定年後再雇用者が活躍できる規程の整備
- 従業員のやる気を削がない賃金規程の整備
お客様の声
以下は弊所で就業規則を作成したお客様からのお声をいただいております。
 株式会社 東開発 常務 粟國修様
株式会社 東開発 常務 粟國修様
今回は、去年の本社の就業規則改定委員会に基づき関連会社2社を作成しました。2020年の4月ごろから開始して、スムーズに作業が進みました。10年ぶりの改定で、現在の状況と合っていない部分も多く、そこを話し合いながら最新の法律に合うように整備しました。その後、社員説明会でどのようになったのか説明しましたが、社員にも喜んでもらえたので非常に満足しています。
特に力を入れた点は労働時間で、変形労働時間制を取り入れ、半日勤務の日を作りました。実態に沿った労働時間になり、また全体の時間数など明確になったので事業の計画も立てられるようになりました。働き方の認識が変わったように感じます。
全国から有志の社労士が大阪に集まり、100年以上続く企業について勉強会が開かれています。江尻事務所も参加しています。
100年企業就業規則勉強会のご報告を見る ›

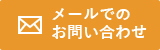






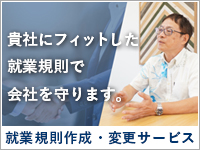


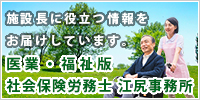
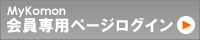

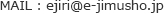

 ■職場の難問Q&A 労働条件・人事・給与 メンタルヘルス・職場の活力 全100Q&A
■職場の難問Q&A 労働条件・人事・給与 メンタルヘルス・職場の活力 全100Q&A